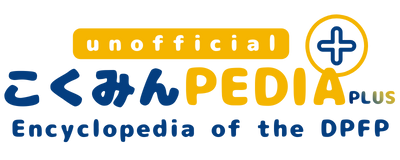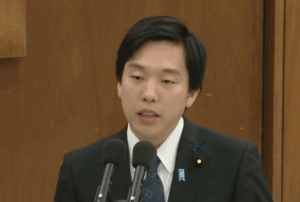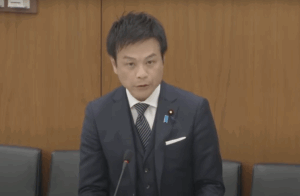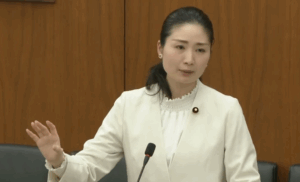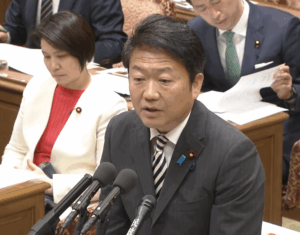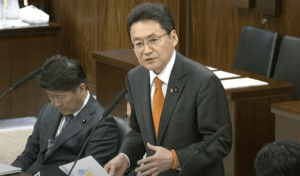質疑者:菊池 大二郎
3行要約
- 菊地議員は日本学術会議の法人化を機に、国民への理解促進と機能強化、特に国会との連携や地方創生への貢献を具体化できるかを問う。
- 坂井国務大臣は、学術会議の知恵が国民生活の向上に繋がるよう改革を進め、組織運営の自由度を高め、事務局体制を強化する方針を示す。
- 信頼関係再構築のため、政府と学術会議は対話を続け、国民に評価される学術会議を目指し、継続的なコミュニケーションを図ることを確認。
1. 概要
本質疑は、日本学術会議の法人化に関する法案について、菊地議員が政府側の認識や課題、今後の展望について質疑を行うものです。議論の中心は、学術会議の独立性、財源の確保、会員の負担軽減、そして国民への理解促進です。
2. 主題・主張
菊地議員は、日本学術会議の法人化に伴い、国民に理解されるよう再定義し、機能強化を図る必要性を主張しています。特に、国会との連携強化や地方創生への貢献といった具体的な活動を通じて、国民がその存在意義を実感できるような組織運営を求めています。
- 法人化後の日本学術会議の国民への再定義と機能強化の必要性
- 国会との連携強化、地方創生への貢献といった具体的な活動の推進
3. 重要な論点
- 日本学術会議と学会・有識者会議との違い: 菊地議員は、個別の政策目的に対して学会や有識者会議による支援で十分ではないかという疑問を呈しました。これに対し、政府側は、日本学術会議が人文社会科学から理工学まで幅広い分野の科学者を擁し、分野横断的な議論を通じて、政府や社会に対して専門的かつ信頼性のある見解を提示できる点を強調しました。また、国際的な学術団体との連携や、G7各国のナショナルアカデミーによる共同声明の発表など、科学者の代表機関としての活動も重要な役割であると説明しました。
- 会員・連携会員の負担軽減と事務局機能の強化: 菊地議員は、会員や連携会員が大学での講義や研究活動に加え、学術会議の業務も兼務している現状に触れ、業務過多による負担を懸念しました。これに対し、政府側は、会員定数の増員や再任制度の見直しを通じて若手研究者の参画を促進し、会員の状況や連携会員の希望を踏まえ、連携会員制度の見直しを検討することを示唆しました。また、事務局の拡充を含め、必要な支援を行う考えを示しました。
- 財源の多様化と国の財政的支援: 菊地議員は、学術会議の財源が限定的であり、民間からの資金調達に偏ることで独立性が損なわれる可能性を指摘しました。これに対し、政府側は、法人化後も国からの補助金による財源確保を基本とし、これまでと同様に予算査定プロセスを経て予算を獲得する方針を示しました。その上で、学術会議自身による財源確保の努力も必要であるという認識を示しました。
4. 結論と展望
結論
日本学術会議の法人化は、組織運営の自由度を高め、活動を活性化させる可能性を秘めている一方で、国民への理解促進、会員の負担軽減、そして財源の確保といった課題を克服する必要があります。
今後の展望
今後は、学術会議が具体的な成果を通じて国民に貢献し、信頼関係を再構築していくことが重要です。
- 学術会議は、国会との連携を強化し、政策提言を積極的に行う。
- 地方創生に資する活動を具体化し、地域社会への貢献を明確にする。
- 若手研究者の参画を促進し、多様な視点を取り入れた活動を展開する。
- 透明性の高い組織運営を行い、国民からの信頼を得る。
5. 評価
本質疑は、日本学術会議の法人化に関する重要な論点を明確にし、今後の組織運営における課題と展望を示唆しています。学術会議の活動を活性化し、社会に貢献していくためには、国民への積極的な情報発信と対話を通じて、その存在意義を理解してもらう必要があります。
用語説明
- サイエンスフォーポリシー: 科学的知見を政策決定に活用する考え方。エビデンスに基づいた政策立案を推進し、政策の質を向上させることを目的とします。
- 連携会員: 日本学術会議の会員と連携して、学術会議の業務の一部を行うために置かれる会員。会員と協力して、提言の審議や地域における活動、国際活動などに参画します。
- Gサイエンス学術会議: G7各国のナショナルアカデミーにより構成される学術会議。地球規模の重要課題について共同声明を取りまとめ、G7サミットに向けて参加各国の首脳に報告を行います。