質疑者:浜口 誠
目次
3行要約
- 船員不足の深刻化と高齢化に対応するため、働き方改革や開示人材の育成支援が重要であり、特に日本人船員の確保が喫緊の課題である。
- 船員の労働環境改善として、船内通信環境の整備を促進し、カーボンニュートラルに向けてゼロエミッション船の開発と代替燃料への転換をIMOと連携して進める。
- EV輸送船の火災リスクに対応し、国際社会と連携して安全対策を強化するとともに、開示人材育成への予算支援を継続していくことを要望する。
1. 概要
テーマは、船員の確保、働き方改革、海上労働環境の改善、開示人材の育成、船舶のカーボンニュートラル、船の安全確保。本会議は、少子高齢化による船員不足や環境問題に対応するため、海事産業の持続可能性を議論することを目的とする。
2. 主題・主張
浜口議員は、船員不足の深刻化、カーボンニュートラルへの対応、船の安全確保の重要性を訴え、政府に対し具体的な対策を求めている。特に、船員数の目標未達、働き方改革の遅れ、開示人材育成の現状、カーボンニュートラル戦略の課題、EV輸送における安全対策について、政府の取り組み状況と今後の展望を質している。
- 日本人船員の確保目標に対する現状との乖離
- 開示人材育成のための学校への支援強化の必要性
- 船舶のカーボンニュートラルに向けた具体的な戦略と課題認識
3. 重要な論点
- 船員確保の現状と対策: 日本人船員の目標数(5500人)に対し、現状は2000人程度と大幅に不足している。政府は、使用者側の理解と関係者の協調を促し、働き方改革を推進することで船員の魅力を高め、多様な人材を海上労働市場に呼び込むことを目指す。具体的には、船員法改正による労務管理の適正化、労働時間短縮、船内作業の自動化、通信環境の改善などを努力義務として求める。
- 開示人材の育成: 開示人材育成機関(商船系大学等15校、水産高校42校)の定員は横ばいまたは減少傾向にあり、入学者数も減少している。政府は、会議教育機構における船員養成に必要な予算確保、入学定員の拡大、日本船舶船員確保計画制度の創設、6級会議士短期養成コースの創設などを通じて、開示人材の育成を支援する。内航船への新規就業者が増加するなど、一定の成果も見られる。
- 船舶のカーボンニュートラル: 国際海運における温室効果ガス排出ゼロという国際目標(2050年頃)に向け、政府はゼロエミッション船等の技術開発・普及を推進し、IMOにおける国際ルール策定に戦略的に関与する。具体的には、グリーンイノベーション基金を活用したアンモニア・水素燃料船の開発支援、GX経済個債を活用した生産設備投資への支援などを実施する。IMOにおいては、代替燃料への転換を促す制度を導入する条約改正案が基本合意されている。
4. 結論と展望
結論
浜口議員の質問と政府の答弁を通じて、船員不足、開示人材育成、カーボンニュートラル、船の安全確保といった海事産業が抱える課題が明確になった。政府は、これらの課題に対し、法改正、予算措置、国際連携などを通じて対策を講じているものの、目標達成には更なる努力が必要であることが示唆された。
今後の展望
今後は、
- 船員確保に向けたより実効性のあるインセンティブ制度の導入
- 開示人材育成機関への更なる支援強化と魅力的な教育プログラムの開発
- カーボンニュートラルに向けた技術開発の加速と国際的なルール形成への積極的な貢献
- EV輸送における安全対策の強化と国際社会との連携 などが求められる。
5. 評価
本会議の内容は、海事産業の持続可能性を確保する上で極めて重要である。特に、少子高齢化による船員不足、地球温暖化への対応、安全確保は、喫緊の課題である。本会議の内容は、海事産業に関わる政策立案者、業界関係者、研究者にとって有益であり、今後の政策決定や研究開発の方向性を示す上で重要な情報源となる。ただし、政府の対策が実際に効果を発揮するかどうかは、今後の実施状況を注視する必要がある。
用語説明
- 外交日本船舶: 外国との貿易に従事する日本籍の船舶。日本の経済安全保障の観点から、その確保が重要視されている。
- ゼロエミッション船: 航行時に温室効果ガスを排出しない船舶。アンモニア、水素などの代替燃料を使用する。
- 海事産業強化法: 船員の労務管理の適正化、労働時間の短縮など、船員の働き方改革を推進するために制定された法律。


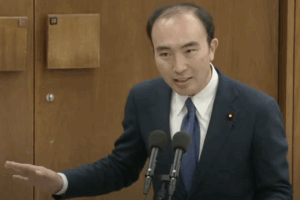
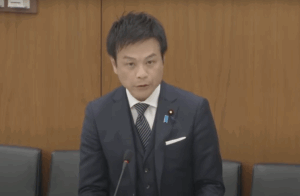


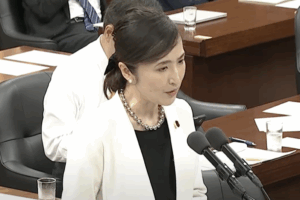
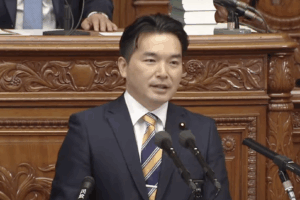

コメント