質疑者:丹野 みどり
目次
3行要約
- 丹野議員は、公益通報者保護法改正を評価しつつ、公益通報者の範囲拡大、小規模事業者への配慮、探索行為への罰則、不当な配置転換への対策など、更なる改善を求めました。
- 藤本総括審議官は、公益通報者の周辺者保護は状況注視、小規模事業者への保護要件緩和は行政負担増の懸念、探索行為への罰則は慎重な検討が必要と回答しました。
- 配置転換については、個人の主観に依存する要件での罰則や立証責任転換は困難としつつ、資料持ち出し時の免責についても慎重な検討が必要と答弁、議論の継続を約束しました。
1. 概要
テーマは、公益通報者保護法の改正に関する課題と今後の展望。丹野議員は、法改正の意義を認めつつも、不十分な点や更なる改善の必要性を指摘し、政府側の見解を質す。
2. 主題・主張
丹野議員は、公益通報者保護法の改正は一歩前進であると評価しつつも、公益通報者の範囲、事業者の規模、探索行為の抑制、不当な配置転換への対策など、実効性を高めるための課題が残ると主張。特に、小規模事業者の通報のしやすさ、犯人探しへの罰則、不当な配置転換の定義と立証責任の転換について、更なる検討を求めている。
- フリーランスが公益通報者の範囲に追加されたこと、探索行為の禁止が明文化されたこと、解雇・懲戒に対する刑事罰導入、裁判時の立証責任転換は評価できる。
- 証言してくれる同僚や取引先など、公益通報者の範囲拡大を検討すべき。
- 小規模事業者が行政機関に通報しやすくする要件緩和を検討すべき。
3. 重要な論点
- 公益通報者の範囲拡大: 丹野議員は、フリーランスが保護対象となったことを評価しつつ、証言してくれる同僚や取引先など、通報を裏付ける協力者も保護対象に加えるべきだと主張。現状では、通報者本人以外の周辺人物は保護されておらず、証言を躊躇する可能性があると指摘。政府側は、実態が明らかでないため状況を注視するとしている。
- 小規模事業者への対応: 丹野議員は、300人以下の事業所に対する体制整備が努力義務である現状に対し、労働者数要件を引き下げ、小規模事業者が行政機関に通報しやすいよう要件を緩和すべきだと提案。社員数が少ないほど内部通報体制の構築が難しく、通報者が特定されやすいという課題を指摘。政府側は、2号通報の保護要件が緩和されていること、更なる緩和は行政機関の負担増につながる懸念があることから、難しいとの見解を示した。
- 探索行為と不当な配置転換: 丹野議員は、公益通報者を特定する行為(犯人探し)の禁止規定にある「正当な理由がなく」という文言が曖昧で、事業者に悪用される可能性があると指摘。また、不当な配置転換に対する罰則や立証責任の転換に関しても、具体的な要件設定の難しさから、議論が平行線を辿っている。政府側は、Q&A等で解釈を明確化するとしているが、罰則導入には慎重な姿勢を示している。
4. 結論と展望
結論
公益通報者保護法の改正は、公益通報者の保護を強化する上で重要な一歩だが、実効性を高めるためには、公益通報者の範囲拡大、小規模事業者への対応、探索行為の抑制、不当な配置転換への対策など、更なる検討が必要である。
今後の展望
今後は、事業者や労働者への周知徹底を図りながら、制度の運用状況を注視し、課題点を洗い出す必要がある。特に、小規模事業者が通報しやすい環境整備、犯人探しに対する罰則の導入、不当な配置転換の定義と立証責任の転換について、社会の実情を踏まえた議論を重ね、より実効性の高い制度へと改善していくことが望まれる。
5. 評価
本質疑応答は、公益通報者保護法の課題を浮き彫りにし、今後の法改正に向けた議論の方向性を示唆する点で重要である。本内容は、企業のコンプライアンス担当者、労働組合、行政機関など、公益通報者保護に関わる幅広い関係者にとって有益である。留意点としては、個別の事案ごとに判断が異なる場合があるため、法律の専門家への相談を推奨する。
用語説明
- 公益通報: 事業者内部の法令違反行為について、労働者等が不正の是正を期待して、事業者内部、行政機関、報道機関等に通報すること。本件では、公益通報者を保護するための法改正が議論されている。
- 立証責任の転換: 通常、訴訟においては、自己に有利な事実を主張する側がその事実を立証する責任を負うが、立証責任の転換とは、その原則を覆し、相手方に立証責任を負わせること。本件では、不当な配置転換があった場合に、企業側に不当でないことを立証させることを指す。
- メンバーシップ型雇用: 職務内容や勤務地を限定せず、企業が従業員を幅広く採用し、配置転換や異動を通して育成していく雇用形態。本質疑応答では、ジョブ型雇用と比較して、不当な配置転換の判断が難しいという点が議論されている。
※AIによる要約のため、誤りがある可能性があります。
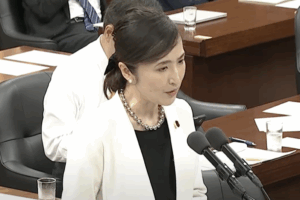


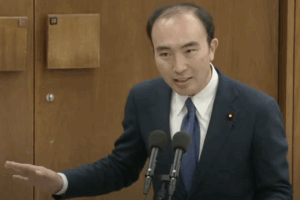
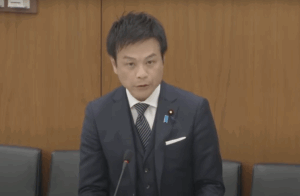


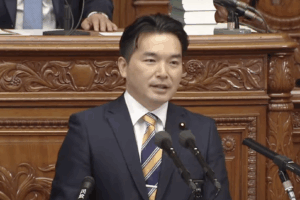

コメント