質疑者:村岡 敏英
目次
3行要約
- 物価高騰に対応するため、農産物の適正価格転嫁に向けた法案の実現可能性と、多様な農業形態への配慮が議論された。
- コスト指標の策定、卸売業者への働きかけ、消費者への理解促進が課題として挙げられ、食料システム全体での連携強化が重要とされた。
- 米不足と価格高騰の原因究明と対策、及びトランプ関税への対応について、江藤大臣は国益を守る覚悟を示し、政府全体で取り組む姿勢を強調した。
1. 概要
本質疑は、ロシアのウクライナ侵攻等による物価高騰が農家の経営や消費者の生活を圧迫している現状を踏まえ、農産物の適正価格転換を目的とした法案について、その実現可能性や課題を農林水産省に問い質すことを目的としています。
2. 主題・主張
村岡議員は、物価高騰の中で農産物の価格転換が困難な現状を指摘し、法案における「費用の考慮」に関する誠実な協議義務の実効性に疑問を呈しています。特に、生産者のコストを適切に反映させるための具体的な計画や、各取引段階における納得感を醸成するための施策について、農林水産省の見解を求めています。
- 生産者のコストが消費者に反映されるまでの過程における課題の明確化
- コスト指標策定における客観性および多様な農業形態への配慮の必要性
- 消費者への理解を深めるための情報発信の強化
3. 重要な論点
- コスト指標策定の実現可能性と客観性: フランスの事例を参考に、専門職業間組織によるコスト指標策定の重要性を指摘。日本の法案では指定作成団体の認定申請に留まっており、客観性が担保されるか懸念を表明。小規模経営や有機栽培など、多様な農業形態に配慮した指標の必要性を強調。
- 各取引段階における納得感の醸成: 生産者、卸売業者、小売業者、消費者という各段階でコストが適切に反映されるためには、それぞれの納得感が不可欠であると指摘。特に卸売業者に対しては、生産者の努力や品質向上への貢献を理解してもらう必要性を訴え、農林水産省が情報伝達の役割を担うべきと主張。
- 消費者への理解促進と購買力向上: 消費者の理解を得るためには、コスト構造の見える化や生産現場の実態を伝えるだけでなく、フェアプライスプロジェクトなどの予算措置も活用する必要性を強調。加えて、賃上げやガソリン減税など、消費者の購買力を高めるための政府全体の取り組みが不可欠であると訴え。
4. 結論と展望
結論
本質疑では、物価高騰という喫緊の課題に対応するため、農産物の適正価格転換に向けた法案の実効性を高めるためには、コスト指標の客観性確保、各取引段階における納得感の醸成、消費者への理解促進が不可欠であることが明確になりました。
今後の展望
今後は、コスト指標策定団体の認定要件の明確化、多様な農業形態に対応した指標のバリエーション拡充、卸売業者への情報提供強化、消費者への継続的な情報発信、購買力向上のための経済対策などが求められます。法案の実行段階においては、関係者の意見を十分に反映し、実態に即した施策を展開していく必要があります。
5. 評価
本質疑は、食料安全保障の重要性が高まる中で、農家の経営安定と消費者の負担軽減の両立を目指す上で重要な議論であり、法案の具体化に向けて建設的な提言がなされました。特に、生産現場の実態を踏まえた情報発信の強化や、消費者の購買力向上に向けた経済対策との連携は、今後の政策立案において重要な視点となります。
用語説明
- 産業連環表: 各産業間の財・サービスの取引関係を示す統計表。本質疑では、農産物が生産者から消費者に届くまでの各段階における取引額を把握するために参照されています。
- フェアプライスプロジェクト: 農林水産省が実施する、食料の価値や価格について消費者の理解を深めるための取り組み。インターネット動画配信やイベント開催などを通じて情報発信を行っています。
- 緑の食料システム戦略: 持続可能な食料システムの構築を目指す政府の戦略。有機農業の推進や環境負荷低減など、環境に配慮した農業への転換を促進しています。
※AIによる要約のため、誤りがある可能性があります。



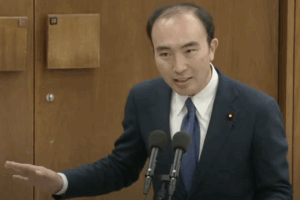
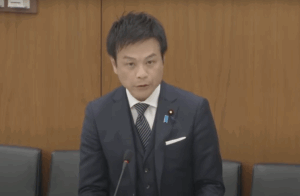


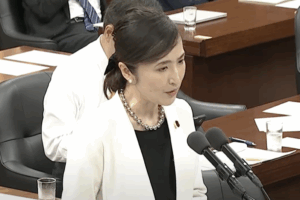
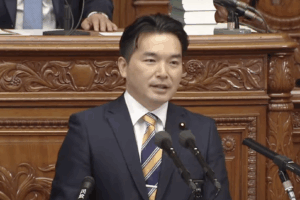
コメント